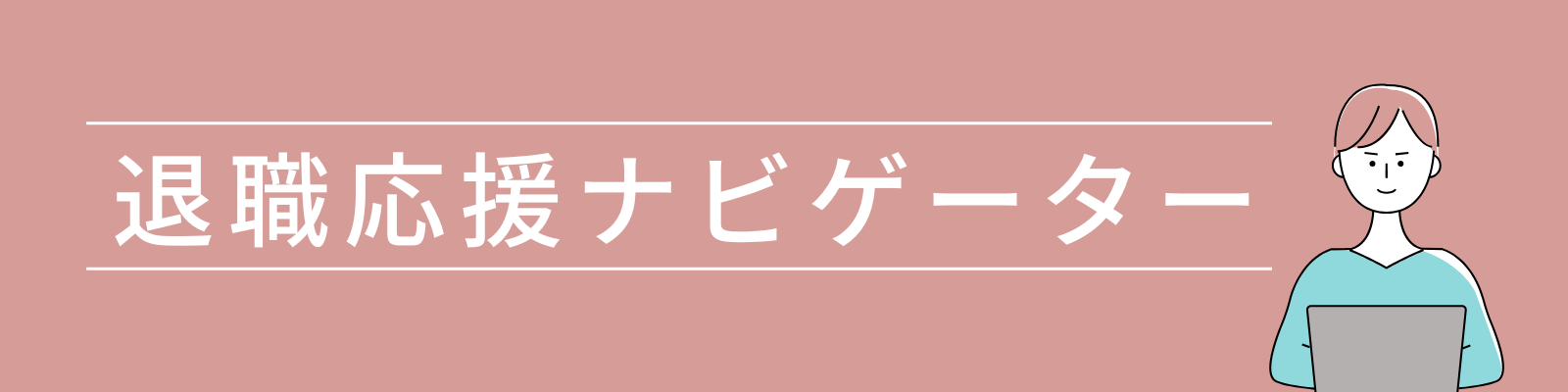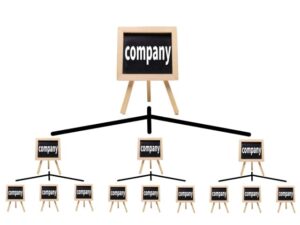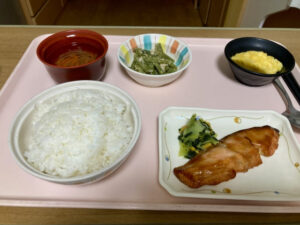「子どもが好きだから保育士になったのに、最近は子どもを見るのもツラい…」そんなふうに悩んでいませんか?
保育士として働く中で、言うことを聞かない子どもや叫び声にイライラすることもありますよね。
また、親の対応に苦しむうちに「もう無理だ」と感じる方も少なくありません。
この記事では、保育士が子どもを嫌いになる具体的な事例を紹介。
また、保育士が退職するときのポイントについても紹介しています。
子どもが嫌いで、保育士を辞めたくて悩んでいる人はぜひ最後まで読んでみてください。
年度途中でももう限界で辞めたいなら退職代行ガーディアンを使うとあなたが「辞めたい」と思ったその日に辞められます。
LINEで無料相談もできるので、まずは退職について気になることを聞いてみましょう。
保育士を辞めたい…子どもが嫌いになる保育士はたくさんいる!

「保育士なのに子どもが嫌いなんてひどいのかな…?」と悩んでいませんか?
保育士をしていて、子どもが嫌いになる人はたくさんいるので自分を責めなくても大丈夫。
具体的に以下の事例があります。
- 事例①言うことを聞かない子どもや相性の悪い子どもにイライラする
- 事例②泣き声や叫び声を毎日毎日聞くのがツラくて限界
- 事例③親がモンスターペアレントだとその子ども自身もかわいいと思えない
それぞれについて詳しく紹介します。
子どもを嫌いになった自分を責めている人は、全く悪くないので安心してくださいね。
事例①言うことを聞かない子どもや相性の悪い子どもにイライラする

子どもは純粋でかわいい存在と思われがちですが、保育の現場ではかわいいだけではありません。
言うことを聞かない子どもや、何を言っても反抗する子どもに出会うとイライラがつのることもあるでしょう。
特に相性が合わない子どもとは、関わるたびにストレスを感じてしまいます。
「どうしてこの子だけ特別に手がかかるんだろう…」と感じることもあるはず。
このようなストレスは、保育士として真剣に取り組んでいるからこその悩みでもあります。
事例②泣き声や叫び声を毎日毎日聞くのがツラくて限界

保育士の仕事では、日常的に泣き声や叫び声を聞く機会が多くなります。
最初は慣れると思っていても、毎日その声に囲まれていると精神的に疲れてしまうもの。
特に保育士は子どもの泣き声や叫び声に対応しなくてはならないため、「何とかしなければ」と思うことでストレスが溜まってしまいますよね。
このような環境では、仕事の楽しさを感じる余裕を失ってしまい、どんどん子どもがかわいくなくなっていきます。
事例③親がモンスターペアレントだとその子ども自身もかわいいと思えない

モンスターペアレントの存在も、保育士が辞めたくなる理由の一つです。
親の要求が過剰だったり、不当なクレームを受けたりすると、その親の子どももかわいいと思えなくなります。
子どもを見ると、大嫌いな親の顔がチラつき、どうしても嫌悪感を抱いてしまうのは仕方のないこと。
こうした状況が続くと、仕事へのモチベーションを保つのが難しくなります。
保育士が向いていないと思うなら退職を決意してOK

子どもが嫌いで、保育士に向いていないと思うなら、退職を決意してもOKです。
理由は以下の3つあります。
- 子どもを嫌いなまま関わってもお互いにとってストレス
- 子どもは敏感。嫌いな気持ちは伝わるから関係が悪化する前に退職しよう
- あなたには合わなかっただけなので自信をなくす必要なし
それぞれについて詳しく解説します。
保育士を辞めたいと思っている人はぜひ参考にしてみてください。
子どもを嫌いなまま関わってもお互いにとってストレス

子どもを嫌いと思いながら関わっていると、ストレスが溜まり、困っていませんか?
イライラした状態では、子どもと良い関係を築くのが難しくなる上に、仕事中もストレスがたまり続け、いいことがひとつもありません。
保育士としての役割を果たすのが苦痛になってしまう場合、無理をせず退職をしましょう。
子どもは敏感。嫌いな気持ちは伝わるから関係が悪化する前に退職しよう

子どもは大人の感情に非常に敏感です。
「嫌いだ」と思う気持ちは、表情や態度、声のトーンを通して自然と伝わります。
その結果、子どもが保育士に心を開かなくなり、関係がさらに悪化してしまうことも。
関係がさらに悪化する前に、あなた自身と子どものためにも退職を検討するのが良いでしょう。
あなたには合わなかっただけなので自信をなくす必要なし

保育士という仕事が「向いていなかった」と感じても、それはあなたの能力や価値がない、というわけではありません。
人には向き不向きがありますし、たまたま保育士という仕事が合わなかっただけ。
実際に、保育士から他の職種に転職して成功している人はたくさんいます。
あなたにも、自分に合った新しい道が見つかるので、今の状況から抜け出すために退職を決意するのはむしろプラスだと考えましょう。
担任制度があるからこそ大変。保育士が退職するときのポイント

保育士は担任制度があるからこそ、退職時に気をつけたいポイントがあります。
具体的には以下の3つのポイントを抑えておきましょう。
- 年度末の切り替えの時期に辞める
- 年度途中で辞めるなら次の担任に引き継ぎをする
- 担任を持っているなら最低でも3ヶ月前に申告する
それぞれについて詳しく解説します。
退職時のポイントが気になる人は、ぜひ参考にしてみてください。
年度末の切り替えの時期に辞める

保育士が退職するなら、できるだけ年度末に辞めるのが理想的です。
この時期はクラス替えがあるため、子どもや保護者への影響を最小限に抑えることができます。
また、年度末退職であれば引き継ぎもしやすく、職場内での混乱も少なくすむでしょう。
年度途中で辞めるなら次の担任に引き継ぎをする

どうしても年度途中で辞める場合は、次の担任への引き継ぎをしっかり行いましょう。
子どもたちの生活リズムや特性、保護者の情報などを丁寧に伝えることで、子どもたちがスムーズに新しい環境に慣れることができます。
引き継ぎの内容をメモや資料として残しておくと、後任の負担を軽減できるでしょう。
担任を持っているなら最低でも3ヶ月前に申告する

担任を持っている場合、退職の意向を伝えるのはできるだけ早い方が良いです。
特に3ヶ月前には申告するのが理想的です。
十分な期間があれば、次の担任を選ぶことや引き継ぎの準備がスムーズに進みます。
円満退職のためにも、早めに職場へ相談するようにしましょう。
ただし、子どもが嫌いな気持ちでいっぱいで、ストレスでどうしようもないなら即退職を決意してOK。
退職代行サービスを使えば、あなたが辞めたいと思ったその日から保育園に行かなくて良いです。
年度途中で退職したいなら退職代行を使うとすんなり辞められる

どうしても年度途中で辞めたい場合は、退職代行を利用するのも一つの方法です。
子どもが嫌いな状態で毎日関わっていると、ストレスがどんどんたまっていき、あなたの心と身体を壊していくかもしれません。
退職代行ガーディアンなら、24時間365日、LINEで無料相談ができます。
「年度途中に辞めてもいいのか」、「担任を持っているけどどうしたらいいのか」など、退職で気になることがあればまずは相談してみましょう。
以下の青文字をクリックすると退職代行ガーディアンの公式サイトが見えるので、サイトをチェックしてみてください。